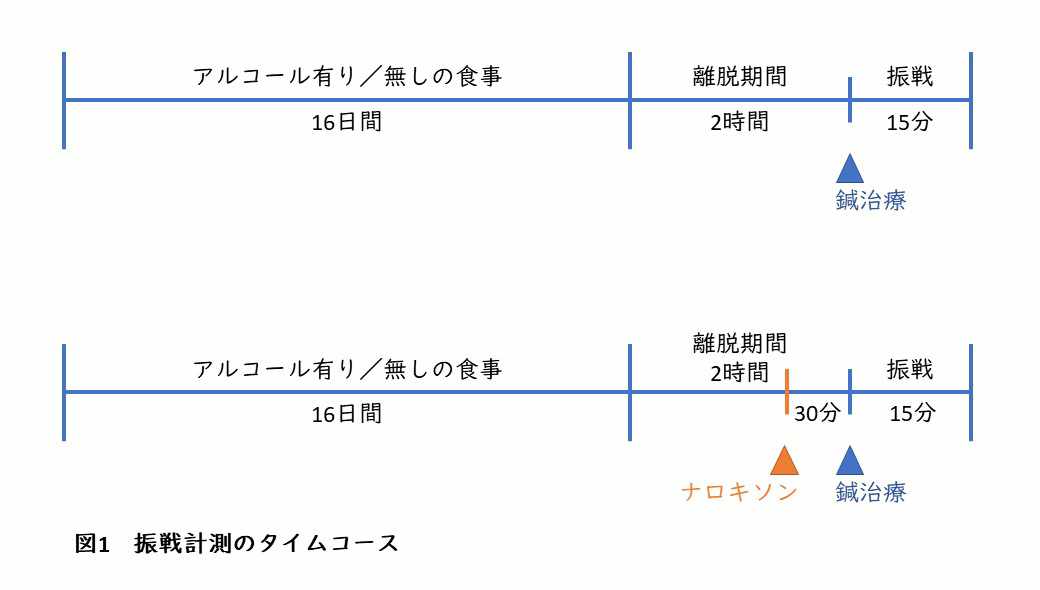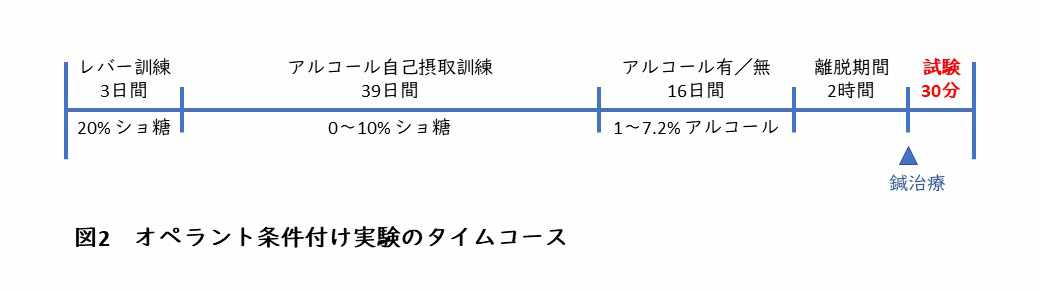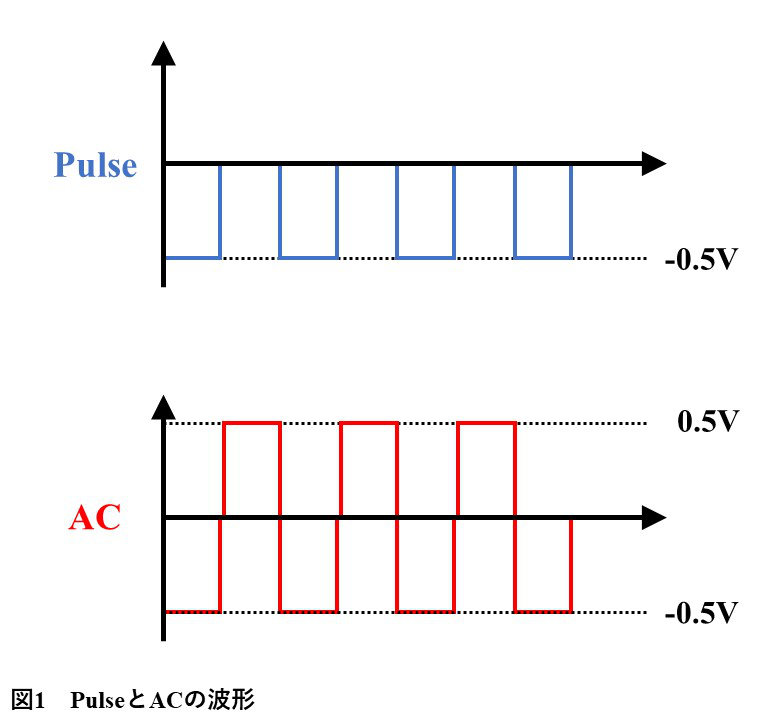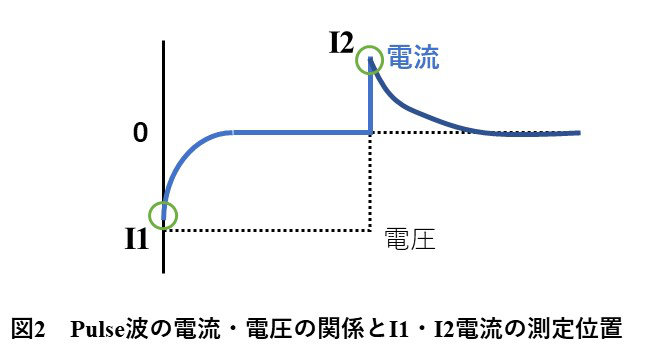季節の移り変わりに見る〈気〉
前回、私は、中国医学の病態認識形成の特徴として三つの点を指摘した。
第一は体内にある臓器や血液などの解剖学的実体を、その〈物〉としてのイメージを引きずったまま不可視の〈気〉に転じたこと、第二はそれを陰陽五行説でカテゴリー化したこと、第三は自覚的あるいは他覚的な生理的・病理的現象(外形)を、カテゴリー化された〈気〉の体系によって解析し、説明したことである。この解析と説明こそ、現在いうところの蔵象学であり、病証学である。
ところで、こうした〈気〉による現象の解釈は、中国医学に特有のものではなく、中国古代の自然学の認識の一つにすぎない。〈気〉と現象の表れは、たとえば春夏秋冬とその変化に対する認識の中に典型的に現れている。
たとえば、春の気候は、〈春気〉の働きとされる。しかし、〈春気〉なるものは存在しない。暦は春とはいえ、なお真冬と変わらない厳しい寒さ、晩秋から初冬には見られない空の明るさ、地表における雪の消失、氷解による河川の水量の変化、草花は芽生え、樹木は花を咲かせ、野山を美しく彩り、それまで何カ月も見ることのなかった虫や動物が姿を見せる……。東アジアの季節の歳時記というべき七十二候に「東風解凍(はるかぜ、こおりをとく)」、「魚上氷(うお、こおりをはいずる)」、「桃始笑(もも、はじめてさく)」と美しく表現される、その総体が〈春気〉の実体である。
こうしたことからもわかるように、原因であるはずの〈気〉とは、実は一定の現象の総和、結果なのである。
中国の〈気〉の自然学には、いくつかの特徴がある。一つはその時節にふさわしい一定の現象が様々なカテゴリーで横断的、かつ一斉に起こるということである。もう一つは、この〈気〉には時間的変遷がある。つまり時間の経過とともに、その〈気〉の極点において別の〈気〉に移行する。
春は夏に変わり、秋は冬へと移行し、終わりなく循環する。この時間的な変化こそ、自然界における〈気〉の存在の根拠である。この変遷は寒暑や春夏秋冬、二十四節気、七十二候、あるいは「五運」や「六気」など様々に呼ばれる。
ただし、同時に忘れてはならないことは、その法則や循環(順)には、そこからの逸脱(逆)という要素が常態として織り込まれているということである。寒冷の夏や温暖の冬がそれである。それらは個々の場面では異常であるが、長い時間のスタンスの中では常態である。順と逆は対立しながら、実は一つのものの両面である。
ポイント
- 〈気〉による現象の解釈は、中国古代の自然学の一つ!
- 春夏秋冬、時間的な変化は自然界における〈気〉の存在の根拠!
- 寒冷の夏や温暖の冬のような「逆」の要素が常にある!
中国医学古典による人体内の〈気〉の説明
一方、人体の〈気〉、つまり〈内気〉と生理現象あるいは病症状を説明する方法は、自然を説明する場合よりも、一層複雑である。
〈内気〉のカテゴリー化とは、〈気〉をただ一つと見なさず、〈内気〉を構造化し相互に関係づけることによって、病態を構造的に把握しようとする考えにつながっている。こうした考え方は、症状や病名に特効穴や特効薬を直接結びつける経験治療や、一つの〈気〉の滞りや偏りをもって病態の根本原因とする〈一気留滯〉的な考えとは対照的である。
中国医学古典の中に見られる〈内気〉には、深部の五蔵六府、表層の経脈、そして〈内気〉の様々な変形である精神、気血、営衛、津液などがある。また病理の分野では痰飲がある。しかし、古来、〈内気〉の第一と考えられてきたのは、五蔵である。
五蔵の蔵象は、『素問』『霊枢』『難経』『傷寒論』『金匱要略』の諸篇に散見するが、蔵象の条文は『素問』に顕著である。特に金匱真言論、陰陽応象大論、霊蘭秘典論、六節蔵象論、五蔵生成篇、宣明五気篇、五運行大論などには総括的な記載が見られる。
『素問』の最初の部分に蔵象の記載が集中しているのは、現行本『素問』の再編者である王冰の意図が働いていると考えられる。
なお、これまでしばしば使ってきた「蔵象」という言葉は、六節蔵象論に見られるものである。
『霊枢』では本輸、邪気蔵府病形、本神、本蔵、五味の諸篇に比較的まとまった記載が見られる。
この『素問』『霊枢』に見える蔵象については、唐代では楊上善『黄帝内経太素』巻第六・蔵府之一が、宋元以降では朱丹溪『素問糾略』形体蔵府性情略、滑寿『素問鈔』蔵象、張介賓『類経』蔵象類、李中梓『内経知要』蔵象、汪昂『素問霊枢類纂約註』蔵象などが五蔵およびその他の関連条文を集めて注解を加えており、参考になる。
『素問』『霊枢』諸篇に述べられた藏象は、蔵の陰陽(陽中の陽は心など)、蔵府の表裏関係、蔵府と経脈の関係といった基礎論から、五主(筋脈肉皮骨)や五竅(目舌唇鼻耳)、五神(魂神意魄志)、五色(青赤黄白黒)、五味(酸苦甘辛鹹)、五液(涙汗涎涕唾)など五蔵所管の各分野に及んでいる。
また診察の分野で最も重要視されるのは、五蔵の脈証と病証である。特に五蔵の脈診は、春夏秋冬の脈状を土台として行われる。それは五蔵それぞれが、〈気〉という点において、春夏秋冬と対応関係にあるとの認識が根底にあるからである。病証については、その蔵が病んだ場合、あるいは虚実の場合の典型的な病症状を挙げる場合が多いが、『素問』痺論に見られるように、特定の病証を「肺痺」「肝痺」のように五蔵分類するという方法も採用されている。その他、蔵の病には五蔵の間における〈伝変〉がしばしば問題となる。
ポイント
用語解説
王冰(おうひょう): 名は冰、啓玄子と号す。唯一の伝記的資料である『素問』に附された王冰の序文と、それに対する宋臣の注によると、王冰は中国盛唐期(712~765)の官僚で、太僕令に任ぜられ、八十歳あまりで没したという。また当時流行していた『素問』に先師張公家蔵の「秘本」を参照して校訂と注解を行うとともに、養生関係の諸篇を最初に移すなどの大幅な構成の変更によって道教風に一変させて、宝応元年(762)に序文を記した。『素問』を現在に伝えた功績のある一方、第六十六篇から七十四篇に至る所謂「運気七篇」を補入したとの説もあり、毀誉褒貶の評価が絶えない。なお王冰の他の著作は早くに佚亡し、現存する『素問六気玄珠密語』『元和紀用経』はいずれも偽作と考えられている。
朱丹溪(しゅたんけい):1281~1358。元代の医家。金元四大家の一人。名は震亨、字は彦修、丹溪はその号である。「陽は常に余りあり、陰は常に不足す」の立場から陰虚火動の解消、すなわち陰気(精気、腎)の保養(滋陰)と、相火(肝や腎が持つ陽気)の降下を主張した。伝記資料として、『丹溪心法』に附された宋濂「故丹溪先生朱公石表辞」、戴良「丹溪翁伝」がある。自著は代表作『格致余論』(1347)及び『局方発揮』『本草衍義補遺』の三書にすぎないが、門人や後世医家の編纂した医書に、戴思恭『金匱鈎玄』(1358。一名「平治会萃」)、楊楚玉『丹溪心法』、呉尚黙『丹溪手鏡』、王世仁『脈因証治』、高賓『丹溪治法心要』などがある。
滑寿(かつじゅ):1304?~1386。元末明初の医家。字は伯仁、攖寧生(えいねいせい)と号した(「攖寧」の語は『荘子』大宗師篇による)。『明史』に伝が見えるほか、李濂『医史』巻之八に朱右の手になる長文の伝と治験が見えるが、これは日本の上村二郎右衛門無刊記本や元文六年(1741)本『診家枢要』にも附載されている。代表的著作である『難経本義』(1361)、『十四経発揮』(1341)は日本の江戸期に繰り返し重刊され大きな影響を及ぼした。その他の著作として『診家枢要』(1359)、『読素問鈔』(『黄帝内経素問鈔』『素問鈔補正』)、『五臓方』(日本宝暦七年〔1757〕本)が伝存する。
張介賓(ちょうかいひん):第2回の用語解説参照
李中梓(りちゅうし):1588~1655。明末の医家。字は士材、念莪、凡尽居士と号した。生没年は李中梓の門人・郭佩蘭『本草匯』の記事に基づく。代表的著書である『内経知要』(1642)は『素問』『霊枢』の経文を摘録して八分類とし附注したもので、張介賓の『類経』の縮約版の趣がある。『医宗必読』(1637)は通論、脈法、本草、傷寒、雑証からなる医学全書である。また『診家正眼』(1642)は、先行する滑寿『診家枢要』、李時珍『瀕湖脈學』、呉崑『脈語』と並ぶ明代脈書の白眉である。
汪昂(おうこう):1615~1694?。明末清初の医家。号は訒庵。本草や方剤学に優れ、南宋の陳言や明の呉崑の医説を尊重した。代表的著作に後世方剤学の規範となった『医方集解』(1682)、『素問』『霊枢』を類別に分類して注解した『素問霊枢類纂約註』(1689)、常用される薬物の要旨を述べ、『本草綱目』などの不備を補った『本草備要』(1694)がある。
『素問』『霊枢』以降、隋の時代までの五蔵
『素問』『霊枢』の後を承けて著された『難経』では、陰陽や寒熱など様々な問題が扱われているが、やはり医論や脈論の中心となっているのは、五蔵論である。しばしば指摘される『難経』の五行説とは、『難経』の著者が意図的に強調しようとしたものではなく、実は五蔵を論じることによって強いられた結果であると私は考えている。
後漢の頃に成立したとされる最古の兪穴書『明堂』では、五蔵に関わりが深いものとして、『霊枢』本輸篇に基づく手足の五兪穴や、『霊枢』背腧篇をさらに展開したものと考えられる背部兪穴がある。腹部の募穴は『難経』六十七難に「募」一語として登場するが、兪穴や募穴と蔵府の関係を明らかにしたのは、『明堂』が最初である。
後漢のあと、王叔和は『脈経』巻第三の諸篇において、『素問』『霊枢』などから蔵府条文を集約し、さらにそれに現在は佚亡した『四時経』を加えて五蔵五府の病証を整理した。これは最初の本格的な蔵府論の初めであった。
やはり後漢のあとに出たとされる『甲乙経』は、巻之一で蔵府、巻之二で経脈、巻之三で兪穴、巻之四で脈法、巻之五で鍼法、巻之六以降に医論、病論と鍼灸の主治を載せていることから、蔵府論を基礎とする鍼灸書として構成されていることがわかる。
『脈経』以降、本格的に蔵府論を展開したのは、孫思邈『備急千金要方』で、その巻第十一~巻第二十の各巻に、心主を除く十一蔵府を充て、それぞれの蔵象、脈証、病証について詳細に論を展開している。
また同書の巻第二十九・五蔵六腑変化傍通訣第四では、五蔵に所属するカテゴリーを56条の一覧表にまとめ、続く『外台秘要方』巻第三十九・五蔵六腑変化流注出入傍通では、これに更に24条を加えた。
ポイント
用語解説
『難経』(なんぎょう):中国の後漢に成立したとされる医書。古くは「八十一難」「八十一問」などと呼ばれたが、唐代以降、『素問』『鍼経』『明堂』と並んで、「黄帝」の名を冠して「黄帝八十一難経」と呼ばれるとともに、『史記』に見える伝説上の名医・秦越人の著作に擬された。早く三国時代から注解の対象となり、唐代初期に楊玄操が再編注解して、現在の『難経』の祖型が確立した。唐宋までの古注は南宋以降に『王翰林集註黄帝八十一難経』(『難経集註』)にまとめられ、元明以降の新注では滑寿の『難経本義』が最も大きな影響を及ぼした。また宋代以降は、脈書『王叔和脈訣』と併せて注解刊行され、当時の脈学に影響を与えた。
王叔和(おうしゅっか):中国・三国・魏(一に西晋あるいは呉)の太医令。『医心方』巻第二十九、『太平御覧』巻七百二十二に引く高湛の『養生論』によれば、名は熙で、字である叔和をもって行われた。その伝は正史には見えず、前掲『太平御覧』や『甲乙経』の皇甫謐序所載の記事しか徴すべきものがない。諸家の医説、脈論を引いて『脈経』十巻を編纂したほか、『傷寒論』の原型である『張仲景方』十五巻を編纂したとされる。
『四時経』(しじけい):『脈経』巻第三に多数の引用が見える、現在は失われた古医書。「四時経」の引用は、おそらく『脈経』からの引用であろうが、『素問』玉機真蔵論の新校正注にも見える。森枳園は『脈経』から条文を採録して、『四時経攷注』一書を輯佚した。
『甲乙経』(こうおつきょう):12巻。中国の魏晋南北朝に、『素問』『霊枢』『明堂』の三書を再編した鍼灸書。古来、皇甫謐(215~282)の撰とされてきたが、近年、疑義が提出されている。宋以前には『素問』『鍼経』『難経』『明堂』と並ぶ書として、「黄帝」を冠して「黄帝甲乙経」などと呼ばれたが、元明以降は鍼灸書として扱われている。『素問』『霊枢』の校勘資料であるとともに、佚亡した古代の兪穴書『明堂』の復元資料としても重要である。
孫思邈(そんしばく): 581~682。その伝は『旧唐書』と『唐書』に載せられている。『老子』や『荘子』、あるいは百家の説に通じ、傍ら仏説を好んだとされる。朝廷からしばしば召されたが応じず、在野にあって医療や著作に努めた。代表的著作は『備急千金要方』と『千金翼方』であるが、『千金翼方』については若干の疑義がないわけではない。
『外台秘要方』(げだいひようほう):40巻。王燾の撰。中国盛唐期(712~765)の752年成立。『備急千金要方』『千金翼方』と並ぶ唐代の医学全書。各項の冒頭に『諸病源候論』を引いて病機、病因を述べ、次いで方書を引いて治療法を述べるという体例は、その後の医学全書に大きな影響を及ぼした。唐以前の医学文献からの引用で構成され、引用に際しては引用書名が明示されていることから、現在では失われたしまった医書の輯佚資料としても重要である。とりわけ宋改以前の『傷寒論』の古本が引用されていることから、森枳園はそれらを集めて『張仲景方十八巻』を復元している。なお本書については1981年に『東洋医学善本叢書』所収の宋版をもって唯一のテキストとする。従来流布してきた明版とその重刊本は原型を損なっており、使用すべきではない。
『千金翼方』(せんきんよくほう):『備急千金要方』『外台秘要方』と並ぶ唐代の医学全書で、『新修本草』の内容が見られることから、659年以降の著作とされる。189門に方論2900余条を収める。孫思邈が『備急千金要方』を補うために著作したとされてきたが、その構成や内容は『備急千金要方』とは大きく異なっているだけでなく、道家の説を引く例が多いことから、託名の可能性もある。
江戸期の医書にみる日本の五蔵研究
日本では江戸後期、尾張浅井家が主宰する尾張医学館で、「五蔵六腑変化傍通訣」に龔廷賢や滑寿、馬蒔などの諸本から抜粋した「薬性歌括」「諸病主薬」「十四経穴分寸歌」を加えて四書とし、浅井正封の校正編集を経て、天保10年(1839年)に刊行している。幕末の考証医家・森枳園も『素問攷注』の生気通天論の注でこの表をとりあげ、「此の図に据らば則ち一目瞭然、生剋の理、得る可し」と高く評価している。
また江戸の鍼灸の分野では、江戸初期から前期の鍼灸流派・意斎流がこの傍通訣を鍼灸術の根底に置いた。意斎流と関わりのある鍼灸書『鍼灸抜萃』『鍼灸要歌集』には「五臓の色体」という章名も見られる。
わが国独自の言葉であるこの「色体」という言葉は、大正から昭和の初期に五蔵を重要視した沢田健がこの名称を踏襲したことから、昭和時代を通じて「色体表」として広く流布、定着した。ただ、現在の日本の鍼灸用語辞典などではその出自を問うことなく「五行色体表」「五行の配当表」と称するか、まったく取り上げない場合すらもある。
ポイント
用語解説
尾張浅井家(おわりあざいけ): 浅井家はもと京都にあったが、医系三代の浅井周伯(正純)の時、曲直瀨玄朔の門人・饗庭東庵の高弟である味岡三伯(1629~1698)の門人となり「浅井の四傑」として名を挙げた。周伯は『素問』『霊枢』に通じ,浅井家の内経学の祖ともなった。四代の東軒(正仲)の時、尾張藩に招かれて侍医となり、尾張浅井家の祖となった。五代の図南(政直)は『素問』『霊枢』と李朱医学に通じ、医家として盛名を極めた。その後、六代南溟(正路)、七代貞庵(正封)、八代紫山(正翼)、九代九皐(正贇)と続いて江戸後期の医学に存在感を示した。十代国幹(正典)は明治期の漢方存続運動を主導したが敗れ、そこで尾張浅井家は絶えた。
龔廷賢(きょうていけん):1522~1619。明代中期の医家。字は子才、雲林と号した。代々医学を業とする家に生まれ、父・龔信ととともに名医と評された。父の著書『古今医鑑』を補訂刊行(1576)したほか、代表的著作に『種杏仙方』(1581)、『万病回春』(1587)、『雲林神彀』(1591)、『魯府禁方』(1594)、『寿世保元』(1615)、『済世全書』(1616)、『普渡慈航』(1632)などがある。なかでも『万病回春』は日本江戸期の最初の百年間に20回ほども重刊され、広く流布した。刻舟子『万金一統鈔』(1641序、1684刊)、野村謙亨『万病回春発揮』(1693)、苗村丈伯『俗解龔方集』(1694)、あるいは岡本一抱『回春指南』(1688)、『万病回春脈法指南』(1730)、『万病回春病因指南』(1695)、堅田絨造『万病回春名物考』(1799)などは、龔廷賢の医学の影響の大きさをよくあらわしている。
馬蒔(ばじ):中国・明代後期の医家。字は仲化、玄台(一に元台)と号した。万暦年間(1673~1619)に太医院正文に任ぜられた。著書に『素問註証発微』(1586)、『霊枢註証発微』(1588)、『難経正義』(1580)、『脈訣正義』(1588)がある。『註証発微』両書は、宋代以降最初の『素問』『霊枢』に対する本格的注釈であり、特に『霊枢註証発微』は『霊枢』全篇への最初の本格的な注解として高く評価されている。
浅井正封(あざいまさよし):1770~1829。江戸後期の医家。尾張浅井家の第七代。名は正封、貞庵と号した。尾張藩藩医として医療に尽力するとともに、医学館を設立、『素問』『霊枢』『難経』『扁鵲倉公列伝』『傷寒論』『金匱要略』などを講じ、門人は三千人に及んだとされる。1827年以降、仁和寺秘蔵の古巻子本『黄帝内経太素』や『新修本草』を転写させた。著書に子孫が筆記・補足した『方彙口訣』(1865)、『金匱要略口訣』がある。
森枳園(もりきえん): 1807~1885。江戸後期の考証医家。名は立之(たつゆき)、字は立夫、枳園と号し、養真、養竹と称した。祖は御薗意斎の高弟・森宗純である。伊沢蘭軒門人の渋江抽斎の門下となり、安政元年(1854)に医学館講師に任ぜられ、『宋本素問』『医心方』の校刻に従事するとともに、医学館での講義を行った。主要な著書に『素問攷注』(1864)、『傷寒論攷注』(1868)、『本草経攷注』(1857)があるほか、渋江抽斎とともに善本解題書『経籍訪古志』(1856)を撰し、師である伊沢蘭軒の『蘭軒医談』(1856)や狩谷棭齋の『箋注倭名類聚抄』(1883)の刊行にも尽力した。
意斎流(いさいりゅう):織豊期から江戸初期に活躍した鍼家・御薗意斎(1557~1616)を祖とする鍼灸流派。その術を伝える書に森共之(1669~1746)著『意仲玄奥』(1696)がある。病証による選穴と灸法が主流であった古代・中世の鍼灸に対して、腹部による五蔵の診察に基づく施術という決定的な転換を行った。腹部への打鍼(うちばり)という手技でも知られる。夢分斎伝『鍼道秘訣集』(1685)、渡辺東伯『鍼法奇貨』(1680)、安井昌玄『鍼灸要歌集』(1695)など無分流の流れをくむ鍼灸書、あるいは『鍼灸抜萃』(1676)やその後継書である『鍼灸重宝記』(1718)などの啓蒙的鍼灸書も、早い段階で意斎流と分枝した可能性があるが、詳細は未詳。
沢田健(さわだけん): 1877~1938。大正、昭和時代初期の鍼灸師。民間療法、対症療法化していた日本近代の鍼灸に対して、五蔵や色体表を重視することを通じて、古典を土台とする全体治療「太極療法」を提唱し、柳谷素霊や経絡治療家の先駆的存在となった。鍼灸にまつわる奇矯かつ神秘的なその言説は、代田文誌による聞書集『鍼灸真髄』に詳しい。
唐の時代の医書が重視していたこと
ここで唐代の古医書の再編注解における五蔵論について触れておけば、まず唐の初期に『難経』を再編注解した楊玄操は、全体を十三章に分類し、そのうちの五章の章名に「蔵府」を冠している。これは『難経』の五蔵論的性格を踏まえた命名ではあるが、各章名は総合的にみて、適切とはいえない。
初唐期に楊上善が著した『黄帝内経太素』三十巻では、巻第五と巻第六が蔵府の巻となっている。冒頭の諸巻に養生論的内容が置かれていることを別にすれば、その構成は、『甲乙経』にやや類似している。
また同著者の『黄帝内経明堂』十三巻は各巻に一経脈が充てられているが、各巻の冒頭に、おそらく元来の『明堂』にはなかったであろう蔵象の文章が置かれている。これは唐代の蔵府重視を反映したものと見られる。
盛唐期に『素問』を再編注解した王冰の五蔵論重視については既に述べたとおりである。
ちなみに、六朝の成立とも、また五代頃の著作ともいわれ、宋代から明代までの脈学に決定的な影響を及ぼした『王叔和脈訣』もまた、五蔵を中心とする脈書ということができよう。
こうして、五蔵とその蔵象や病証、脈証は、唐代を通じて完備し、元明以降の五蔵論の展開を準備したのである。
ポイント
用語解説
『備急千金要方』(びきゅうせんきんようほう):略称「千金方」。30巻。孫思邈著。中国・初唐(600年代)成立。唐の始めまでに成立した医方書や鍼灸書を集大成した、唐代の代表的医学全書。232門に方論5300余首を採録している。本書には宋改をうけた南宋版(金沢文庫旧蔵本、日本嘉永二年(1849)江戸医学館覆刻本)と、宋改を経ていない『孫真人千金方』(陸心源旧蔵本)の二種があるので注意を要する。
楊玄操(ようげんそう):中国・初唐(600年代)の人。呂広注本『難経』を得て、再編注解し、現在の『難経』の祖型を確立させた。また『黄帝明堂経』を注解し、『宋史』芸文志その他に『素問釈音』『鍼経音』など音釈の書が著録されているが、全て佚亡している。『王翰林集註黄帝八十一難経』(『難経集註』)の序文及び注文中の「楊曰く」部分に佚文を見ることができる。『外台秘要方』巻第三十九に多数見える「楊操音義」や「甄権千金楊操同」の「楊操」も楊玄操への言及とみられる。
楊上善(ようじょうぜん):中国・初唐(600年代)の人で、太子文学の地位にあった。医書への注解として『黄帝内経太素』『黄帝内経明堂類成』があるほか、『旧唐書』経籍志や『唐書』芸文志には楊上善の手になる『老子』や『荘子』の注解書や思想書が著録されている。
『黄帝内経太素』(こうていだいけいたいそ):30巻。楊上善撰注。錢超塵の説によれば、初唐(600年代)後半、662~670年の間に成立。『素問』『霊枢』の経文を19類に分類して附注したものである。経文は唐宋の改変を受けている『素問』『霊枢』よりも古態を遺すことから、その注解も含めて、『素問』『霊枢』の一級の校勘資料、訓詁資料として珍重される。中国では宋元の間に佚亡したが、日本江戸後期に京都の仁和寺で発見され、現在、仁和寺に23巻、武田科学振興財団杏雨書屋には仁和寺からの流出分2巻、計25巻が伝存する。
『黄帝内経明堂』(こうていだいけいめいどう):13巻。楊上善撰注。一名「黄帝内経明堂類成」。中国・唐の前期(600年代)頃に成立。中国古代の兪穴書『明堂経』、またはその唐代の一伝本『黄帝明堂経』に対する注解書。大半は失われ、日本の仁和寺と尊経閣文庫に第一巻のみ伝存する。十二経脈それぞれに一巻をあて、最終巻に奇経八脈を加えて十三巻とし、各経脈に関係する蔵象と所属兪穴について述べている。唐の752年に成立した『外台秘要方』の巻第三十九の主治条文と同様、全て兪穴を経脈に配当し、かつ兪穴ごとに部位や主治、鍼灸法を集約しようとする志向により成立した、唐代の代表的兪穴書である。
『王叔和脈訣』(おうしゅっかみゃっけつ):歌訣形式で書かれた脈書。編者とされる高陽生については六朝の人とする陳言の説(『三因方』)と、五代の人とする王世相の説(『瀕湖脈学』所引)がある。北宋以降、繰り返し注解されるとともに、『難経』と併せ刊行されて、明代までの脈学に大きな影響をあたえた。他方、『脈経』との内容の相違や言辞の鄙俗などの点からの批判も絶えない。